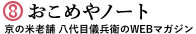最終更新日:2020-11-21
松竹梅は慶事や吉祥のシンボルとして、内祝いの祝儀の席などの図柄になっています。お祝いごとでは品物を三階級に分けた際の等級を示し、松が一番、竹、梅の順になります。
古くから松は冬も青々していることから不老長寿を示す縁起の良い木として尊ばれ、新年を祝う飾りとして門松となりました。この風習は古く平安時代といわれています。
室町時代では松同様冬も青い竹が加わり、江戸時代になり、冬に花を咲かせる梅が門松に加えられました。松竹梅の歴史はとても古く冠婚葬祭でもめでたい時の植物になっています。
結婚式の三々九度で三回に分けて飲む杯を松から竹、梅の順に言ったことから、めでたいとされるようになったという説があります。うなぎ屋や寿司屋は一般的に一番上等が松です。次に竹、梅の順になっています。
お役立ち情報
松竹梅は、縁起の良いものとして慶事に使用されることが多く、贈答品や内祝いなどの装飾などにも使われます。また、ランク分けの順序に使われることもあります。元は中国の画題「歳寒三友」の一つで、松と竹は冬期でも緑々として強いこと、梅は冬期に花を咲かせることから、学者などの理想を表すものとして認識されていました。日本では別な意味として広まり、松が平安時代、竹が室町時代、梅が江戸時代の頃に、それぞれめでたい物の代表として広まったとされています。