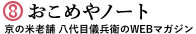最終更新日:2022-08-16
四十九日法要に招かれたら、当日はお香典(現金)やお供え物を持参しましょう。四十九日法要は、初七日から七日ごとに営まれる追善法要の最後で来世への行き先が決まる節目の日のことで、別名「満中陰」とも呼ばれる大切な日です。今回は四十九日法要のお供えの相場や掛け紙など基本のマナーについて、弔事専用ギフトを取り扱う京の米老舗 八代目儀兵衛が解説します。

京の米老舗 八代目儀兵衛
四十九日のお供え物の定番の品物は?
お供えの定番|①お米
お供え物の定番|②供花
お供え物の定番|③線香・ロウソク
お供え物の定番|④果物
お供えの定番|⑤お菓子
お供えの定番|⑥缶詰
【宗教別】お供えで避けた方がいいもの・タブーな品物は?
仏式では「魚介類・肉類・酒」がタブー
神式では「線香」がタブー
キリスト教式では「供物は贈らない」
【四十九日】お供え物の金額の相場
お供えのみの場合
お供えと香典(現金)を両方渡す場合
【四十九日】お供えの掛け紙(熨斗)のマナー
【四十九日】お供えの渡し方のマナー
【四十九日】お供えを郵送する際のマナー
お供えはいつ送る?タイミングは?
お供えに添える手紙は?
手紙の例文
四十九日のお供えで知っておきたいこと
四十九日法要には香典(現金)とお供えの両方が必要?
お供えを辞退された場合は?
真言宗・浄土宗・臨済宗・浄土真宗など宗派による違いはある?
四十九日法要に呼ばれていない場合もお供えは必要?
施主(喪主)側もお供えは必要?
施主(喪主)側はお供え物に対する引き出物を用意すべき?
四十九日法要のお供えもお返し(引き出物)も八代目儀兵衛にお任せください|まとめ
四十九日のお供え物の定番の品物は?
●あとに残らない「消え物」が選ばれています。
四十九日法要に持っていくお供えには、後に残らない「消え物(消耗品)」やお供えをしてから「御下がり」として配りやすい品物が喜ばれます。これは、地域によって、それぞれが持ち寄ったお供えを出席者で分け合うことがあるためです。
食品を持参する場合は「日持ちのしやすさ」にも目を向けることが大切。特に気温が上昇する夏場は、通常よりも食品の劣化も早くなるため、生のフルーツよりも常温で保存できる缶詰、生菓子よりも日持ちのする干菓子やお米のギフトなどがおすすめです。
お供えにもらって嬉しいものといえば?お菓子以外でお考えの方必見、おすすめの贈りもの
お供えの定番|①お米
お米は仏教のお供えの定番である「五供」のひとつであると同時に、神教のお供えとしても親しまれています。
お米というと、お供えとしては少々大きく嵩張るものというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、最近では「御下がり」として配りやすい個包装になったものも多く販売されています。八代目儀兵衛では、四十九日法要のお供えにふさわしい弔事専用ギフトを豊富にご用意しております。
お供え物の定番|②供花
お供え物の定番と言えば「供花」です。四十九日法要までは、白い花を使用することがほとんどで、よほど親しい仲でない限りは差し色は控えるのが通例です。
代表的な供花には、白菊やユリ・胡蝶蘭などの生花や花輪が挙げられます。
バラやヒイラギなど棘のある花や香りの強すぎる花は、お供え物にはタブーです。判断が難しい場合は、専門知識のある花屋に相談するとよいでしょう。そのまま飾れるフラワーアレンジメントなら、喪家に負担をかける心配もありません。
お供え物の定番|③線香・ロウソク
線香やろうそくもお供えの定番です。線香の香は「香食(こうじき)」と呼ばれ、故人にとっての食事にあたります。ロウソクを供えることは、あの世とこの世の架け橋を作ることでもあるのだそう。仏前に供えるなら、いずれも香りが強すぎないものを選ぶようにしましょう。
お供え物の定番|④果物
四十九日のお供えには、華やかな「果物」を組み合わせた盛りカゴも人気です。カラフルなものが多い果物ですが、基本的にはどれを選んでも問題ありません。
ただし、夏場などは傷みやすいバナナなどは避けた方がよいでしょう。リンゴやメロン・梨・グレープフルーツなら常温の保存にも適しています。なお、果物の数については諸説ありますが四十九日のお供えでは「奇数」を選ぶのがマナー。「4(死)」や「9(苦)」など縁起の悪い忌数にならないように注意しましょう。
お供えの定番|⑤お菓子
洋菓子・和菓子ともに、お菓子もお供えの定番です。いずれも賞味期限が長く、個包装になったものが喜ばれます。洋菓子であれば、クッキーやマドレーヌ・フィナンシェ、和菓子であれば、もなかやどら焼き・せんべい・羊羹などが人気です。故人が好きだったお菓子や、ご家族やご親戚に配慮したものを選ぶとよいでしょう。
お供えの定番|⑥缶詰
賞味期限が気になる場合は、お菓子や生のフルーツの代わりにフルーツ缶の盛りカゴを選んでもよいでしょう。缶詰に加えて、ジュースやお菓子が添えられているものも販売されています。親族に小さなお子さまがいらっしゃる場合などにおすすめです。
【宗教別】お供えで避けた方がいいもの・タブーな品物は?
お供え物には、宗教によって贈ってよいものといけないものがあることをご存知ですか?仏教では喜ばれていたものが、別の宗教ではマナー違反になることもあるため事前に確認しておきましょう。
仏式では「魚介類・肉類・酒」がタブー
仏式では、殺生を連想させるとして生の魚や肉類はタブーとされています。お酒に関しては地域や親族の考え方によっても異なるため、避けるのが無難です。
神式では「線香」がタブー
神式では線香を使わないため、お供え物として贈ってはいけません。反対に仏式ではタブーとされていたお酒は贈ってもよいとされています。
キリスト教式では「供物は贈らない」
キリスト教では、お供え物を贈る習慣がないため、基本的には「供花」を贈ります。ユリやカーネーションなど白い花を中心にアレンジメントを依頼するとよいでしょう。
【四十九日】お供え物の金額の相場
お供え物の金額に決まりはありませんが、迷った場合は少し多めを心がけるか、お供え物と一緒に香典(現金)を包むとよいでしょう。
お供えのみの場合
香典を持参せず、お供えのみを用意する場合は、葬儀のときに包んだ5割から7割の金額を目安に品物を選びます。
| 父親・母親(子供の場合) | 1万円から5万円 |
| 祖父・祖母(孫の場合) | 5千円から1万円 |
| 叔父・叔母の場合 | 5千円から1万円 |
| 友人・隣人の場合 | 3千円から1万円 |
| 職場関係の場合 | 3千円から1万円 |
お供えと香典(現金)を両方渡す場合
お供えと香典(現金)の両方を持参する場合は、3千円から5千円を目安にお供え物を選びましょう。香典やお供え物は、家族でまとめて用意して問題ありません。
【四十九日】お供えの掛け紙(熨斗)のマナー
四十九日のお供え物は、弔事に当たるため「熨斗紙」の代わりに「掛け紙」を使用します。
表書きは「御供物」または「御供」とし、水引には黒白または総銀の結び切りを使用します。ただし、関西では黄白の結び切りが用いられることもあるため、心配な方は事前に確認しておくと安心ですね。署名は、贈り主のフルネームを記載するのが一般的です。なお、四十九日以降の墨の色は濃い黒色を使用します。
【四十九日】お供えの渡し方のマナー
お供え物を持参する場合は、勝手に仏壇に供えるのはマナー違反です。紙袋や風呂敷から取り出し、表書きが施主に見えるようにして手渡しましょう。品物をお渡しをした後は、紙袋や風呂敷はたたんで持ち帰ります。
「本日はお招きいただきありがとうございます」「御仏前にお供えください」など一言添えると丁寧な印象になります。
【四十九日】お供えを郵送する際のマナー
四十九日法要に招かれたら、出席するのがマナーです。しかし、妊娠中や体調不良など、やむをえない事情で出席できない場合もあるでしょう。お供えを直接渡せない場合は、手紙や一筆箋を添えてお供え物を郵送します。
お供えはいつ送る?タイミングは?
四十九日法要当日は、施主は会食の準備やお坊さんとのやりとりで何かと慌ただしいものです。
可能であれば、法要の2〜3日前、遅くとも前日には届くように手配しましょう。
せっかく心を込めて選んだお供え物も、法要当日に間に合わないと失礼な印象になってしまいます。お供え物を手配する際には、配達日にも注意を払いましょう。
お供えに添える手紙は?
お供えを郵送で贈る場合、品物だけを届けてしまうと「心がこもっていない」と捉えられてしまうことも。可能であれば、手紙を添えてみましょう。四十九日法要に添える文面には、季節の挨拶や「くれぐれ」「たびたび」などの繰り返し言葉は避け、
| ・法要に招待してもらったことのお礼 ・参列できない場合はお詫びの言葉 ・一緒に届けるお供えについて |
など要点を絞って簡潔にまとめます。
手紙の例文
| この度◯◯様の四十九日の法要のご案内をいただき誠に恐れ入ります。本来ならば、参列させていただくところ、あいにく〇〇(理由)のため、伺うことができぬ失礼をお許しください。心ばかりではありますが、〇〇様がお好きだった(お菓子・お花)をお送りいたします。御仏前にお供えいただければと存じます。謹んでお悔やみを申し上げますとともに 心からご冥福をお祈りいたします。 |
四十九日のお供えで知っておきたいこと
四十九日のお供え物には、複雑なマナーがあり「こんなときはどうすればいいのだろう?」と迷ってしまうことも少なくありません。ここでは、四十九日法要で知っておきたいお供えのマナーについてQ&A形式でご紹介します。
四十九日法要には香典(現金)とお供えの両方が必要?
A 地域や宗教によって異なりますが、一般的にはどちらかでよいとされています。
基本的には香典(現金)かお供えのどちらかを持参するため、お供えのみでもマナー違反にはなりませんが、迷ったら香典(現金)を包むのが無難です。
お供え物や供花は、故人との関係が深い場合に贈るのが一般的です。香典やお供えに関する考え方は親族の考え方によっても大きく異なるため、親しい人に相談しましょう。
お供えを辞退された場合は?
A 基本的には喪家の意向に従います。
四十九日法要の案内にお供え物や供花を辞退する旨が記載されている場合は、喪家の意向に従い、代わりに香典(現金)を包みましょう。
真言宗・浄土宗・臨済宗・浄土真宗など宗派による違いはある?
A 仏教の宗派による違いはありません。
日本にはさまざまな仏教宗派がありますが、仏教であればお供え物のマナーは同じと考えてよいでしょう。
ただし、お供え物と合わせて香典(現金)を包む場合は、不祝儀袋のマナーが異なるため注意が必要です。基本的には仏教であれば「御仏前」または「御佛前」を選びますが、浄土真宗では「故人の魂は死後すぐに成仏する」と考えられているため「御仏前」が使用できません。「御供物料」は宗派を問わず使用できるので、覚えておくとよいでしょう。
四十九日法要に呼ばれていない場合もお供えは必要?
A 呼ばれていない場合はお供えは不要です。
四十九日法要に呼ばれていない場合は、基本的にはお供え物を贈る必要はありません。最近は、同居家族だけで四十九日法要を行うケースも増えています。
故人と親しい関係にあった場合やどうしてもお供え物を贈りたいという場合は、喪家の意向を確認した上で品物を検討するとよいでしょう。
施主(喪主)側もお供えは必要?
A 用意しましょう。
仏壇に飾るお供えは故人への贈り物でもあります。そのため、施主やその家族もお供え物を用意するのが一般的です。日持ちのする消え物や配りやすい個包装になったお供えを用意しておきましょう。
施主(喪主)側はお供え物に対する引き出物を用意すべき?
A 香典やお供え物をいただいたら、お返しとして引き出物をお渡しします。
四十九日法要の出席者から香典(現金)やお供え物をいただいたら、そのお礼として引き出物(粗供養)をお返しします。引き出物の相場は、お供え物や香典の半額から3分の1程度が目安です。お菓子やお茶・海苔・お米など日持ちのする消え物を選びましょう。
四十九日法要のお供えもお返し(引き出物)も八代目儀兵衛にお任せください|まとめ
お仏壇へと持っていくお供えには、不祝儀を後に残さない「消え物」が選ばれる傾向にあります。
仏教のお供え物には「五供(ごく・ごくう)」と呼ばれる「香(お線香)」「花(供花)」「灯明(ロウソク)」「水」「飲食(お米など)」の5つの定番があり、これらに沿って選べばマナー違反になることはないでしょう。
ただし、神式の場合は線香がタブーとされているため、注意が必要です。またキリスト教では、お供えの習慣がないため、代わりに花を贈るようにします。
お供え物の金額は、香典をいくら包むかによっても異なりますが、一般的な相場は3千円から5千円と言われています。迷った場合は親族と相談して、金額を決めてみてください。
京の米老舗八代目儀兵衛では、弔事専用ギフト「偲シリーズ」をご用意しております。2合ずつ個包装になったお米は、仏式や神式でのお供えや「御下がり」にも最適です。弔辞専用の一筆箋など各種無料サービスも充実。手渡しにふさわしい有料の手提げ袋や外包み風呂敷もございます。四十九日法要のお供え物や引き出物も八代目儀兵衛にお任せください。